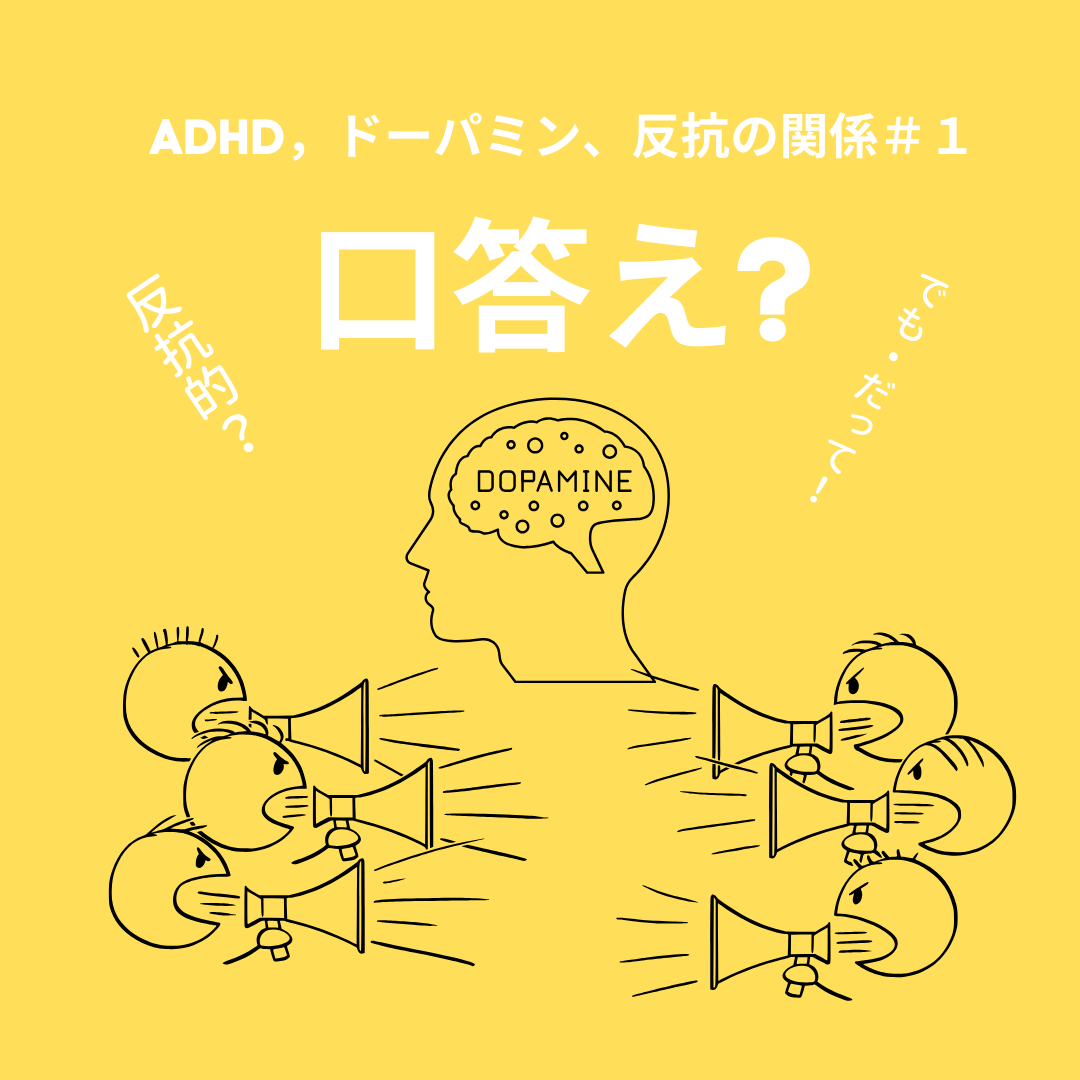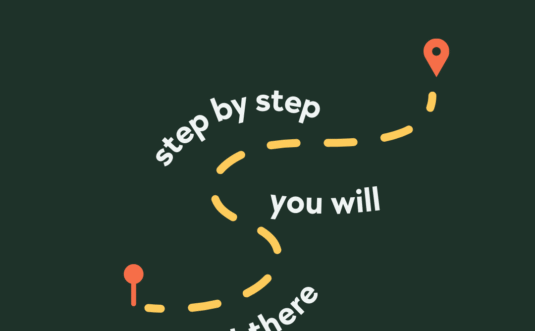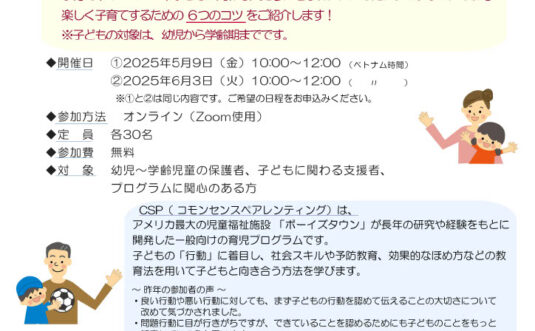ADHDの脳は脳内のドーパミンという神経伝達物質が少なめ、またはその働きが弱いとよく言われています。ADHDの人の薬コンサータを例に取ってみると、ドーパミンが出た元に吸収されるのを防ぐことによって、より多くのドーパミンがニューロンとニューロンの間にとどまり、反対側に吸収されるのを促す役割をします。
ドーパミンは「やる気・快感・ご褒美」に関わる物質です。この不足によって、以下のような特性が現れます:
ドーパミン不足による行動への影響(例)
退屈に耐えられない→ 授業中におしゃべり、動き出す
報酬をすぐに欲しがる→ 待てない、割り込む、我慢できない
感情のコントロールが苦手→ 怒りやすい、口答え、癇癪など
それでは 口答え・反抗はどのようにドーパミンと関係しているのでしょうか?これは、刺激(ドーパミン)を求める行動につながっており、退屈や制限と感じやすいADHDの子どもは、それに対応するため刺激を求めます。
その刺激の1つが、大人との対立や感情の爆発です。
「イライラして口答えする」「親を困らせる」行動が、脳にドーパミンを放出させる刺激になることがあります。つまり、「反抗」や「口答え」は、自分で気づかないうちに脳がドーパミンを得ようとしている行動になることがあります。
また、前回の投稿でも話したように、ADHDの子どもは「感情的に3〜4歳若い」ことも影響しています。「30%ルール」によれば、たとえば12歳の子でも、8〜9歳レベルの感情コントロールしかないことが多く、怒りや不満が湧いたときに、「言い返す・キレる・暴れる」という形で出てしまいやすいことがあげられます。
親や周囲ができるサポートとしては、
感情が爆発する前に気づく →「今イライラしてるね。深呼吸しようか、それとも自分の部屋に行って落ち着いてくる?」
怒っているときは刺激を減らす→ 静かな声、短い言葉で伝える(口論しない)
ドーパミンを健康的に増やす機会を作る→運動、好きな遊び、達成感のある活動をこまめに入れる
ルールより「選択肢」で伝える→ 「すぐ片づける?5分後にタイマーでやる?」など、本人に選ばせる
ADHDの子どもの「口答え」や「反抗」は、単なるわがままではなく、脳がドーパミンを求めているサインのことも。感情をコントロールする脳の部位(前頭前野)が未熟なため、怒りを爆発させやすいと覚えておきましょう。大人が「対立する」のではなく、構造(ルールや流れ)と共感(気持ちへの理解)で支えることがカギです。
次回は、ADHDの子どもの口答えや反抗的な態度を取ったときにどのように対応したらよいか、簡単にお伝えしたいと思います。