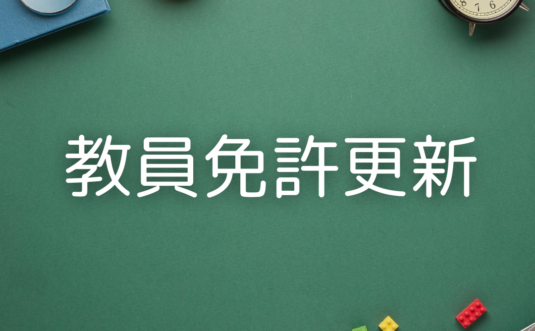子どもにいつも何度も何度も指示を繰り返していると、聞こえてないのかな?耳が悪いのかな?と考えてしまいませんか。聞こえているのにもかからず指示が通らない時は、言語の理解の問題なのか、本人が理解できるように周りが伝えられていないのか、早口だったのか、周りに雑音があるのか、声が小さすぎたのか、他の事に集中しているときや気が散るものがあるときに話しかけているのかなど、色々考える必要があります。
もしかしたら、聞こえには問題がないけれど聴覚処理障害(Auditory Processing Disorder: APD)の兆候があるのかもしれません。APDを診断・治療することは現在困難といわれており、耳鼻科の先生でもチェックリスト(フィッシャー聴覚情報処理チェックリスト・小渕ら聞こえにくさに対する質問紙)を使いADPの可能性があるかどうかを見るだけで、あとは対処していくしかないと言われています。APDは脳の特性と言われているそうで、発達障がいの人にも見られることがあるようです。
まずはAPDの症状を少し理解することから始めてみましょう。
子供が音の意味を処理できない状態や耳で聞いた音と脳が処理する音との間に断絶がある。
聴覚情報を受け取り、記憶し、理解し、利用することができない。
慢性的な耳の感染症、頭部外傷、難産、鉛中毒などが原因となっている可能性がある。
7~8歳まで発達しないこともある。
ADHD、感覚処理問題、ディスレクシアの子どもも聴覚の問題を抱えることがある。
入力言語や受容言語が適切に機能していないため、表現言語に影響が出ることが多い。
それでは、自宅や学校ではAPDの可能性があるかどうか、どのようなことに気をつけて観察すればよいでしょうか。
例えばこのようなこと、気になっていませんか?
指示された後に 「え?」や 「なんだ?」と言うことが多い。
指示に従えない。
現在のトピックとは関係のないコメントをしばしば口にする。
会話についていけない。
言語発達の遅れの可能性がある。
周囲の雑音に気を取られることが多い。
読み、綴り、書きに苦労する。
短期記憶、長期記憶が乏しい。
単語や音の違いが聞き取れない。
教室での注意力や集中力に欠ける。
冗談や話をするのが苦手。
聞こえには問題がなく上記のことが気になることがあれば、本人が生きやすくなるよう工夫をしていきましょう。
こちらには、学校内でできるいくつかの対処法が紹介されています(英語)。また、こちらのクリニックのサイトにはAPDについて説明の説明や工夫が載っていますので、気になる方はこちらのリンクをご覧ください(日本語)。