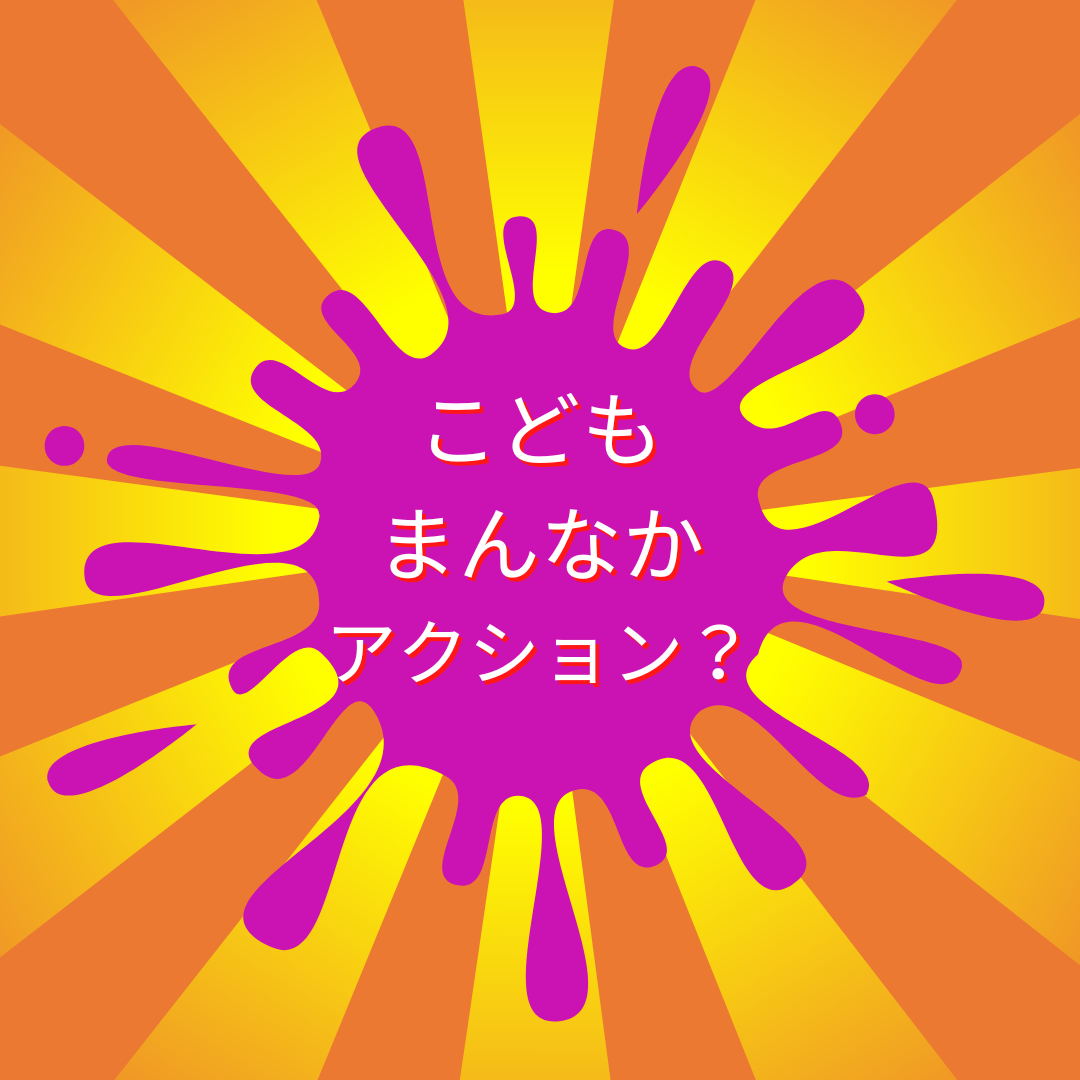『セルフ・アドボカシースキル(Self-Advocacy Skill)』という言葉を皆さんは聞いたことがありますか?
先日のまなびカフェワークショップで、講師のドワイヤーさんもおしゃっていた大切なスキルです。私達親は子どもとずっと一緒にいてあげることができません。幼稚園や小学校の時は子どものことで先生と連絡帳を使ったりコミュニケーションが取りやすかったのが、子どもが成長するにつれて「親がこうしてください!こうだって聞きました!」とは言いにくくなってきます。
そこで大切なのは、子どもが小さいときから子どもの自己理解につながる会話やセルフ・アドボカシースキル(自分の得意、不得意を理解して、苦手を補うために声を上げたり、カバーするスキル)を育てる機会です。このスキルは、短期間で育つものではありません。子ども自身や子どものいるが学習・生活環境も常に変化します。
セルフ・アドボカシーに興味を示していただけた方は、まずはこちらの記事から始めてみてください。
ドワイヤーさんは、「自ら説明し、周りのサポートを得る力」ともおっしゃっていました。
我が家もこのセルフ・アドボカシースキルを大切にしています。