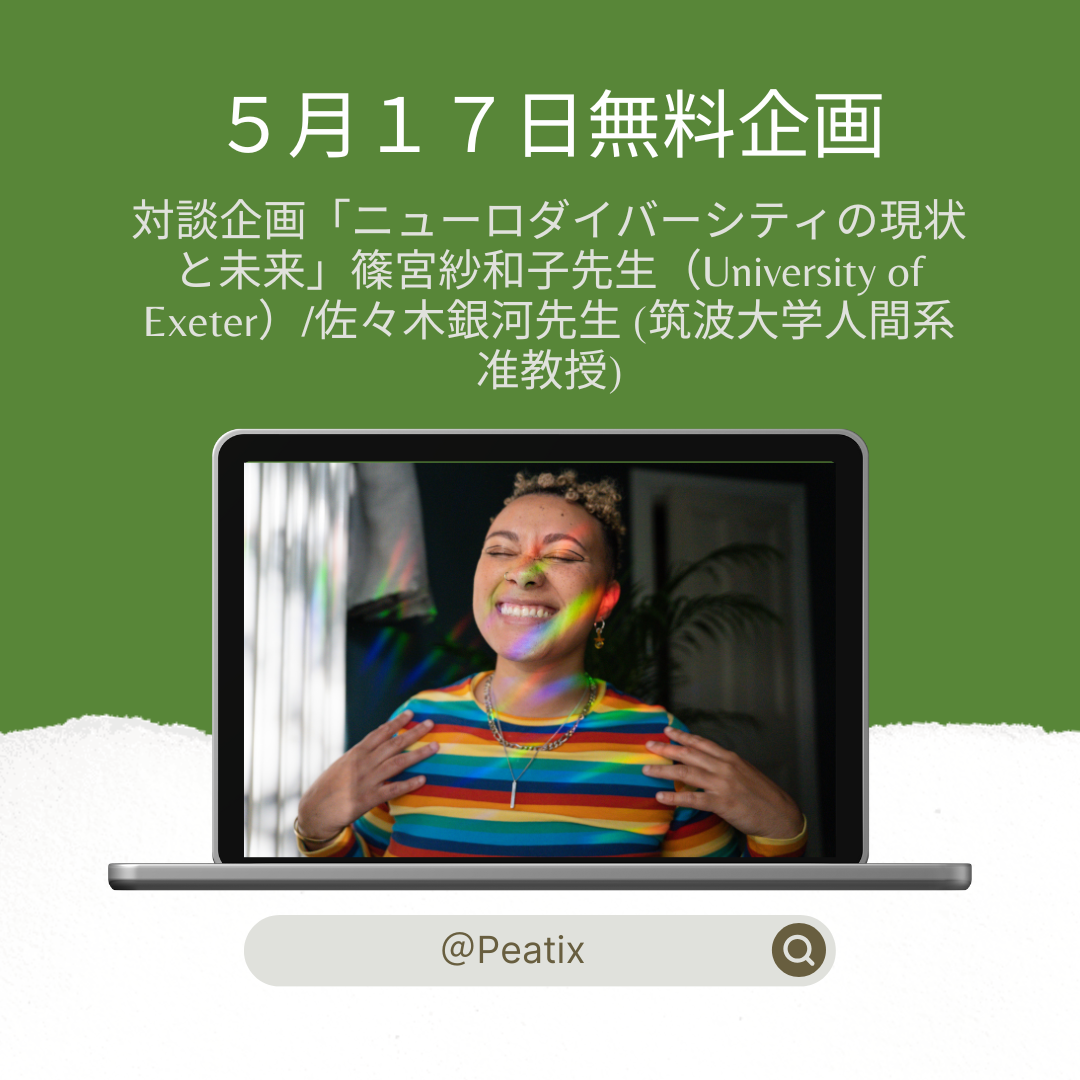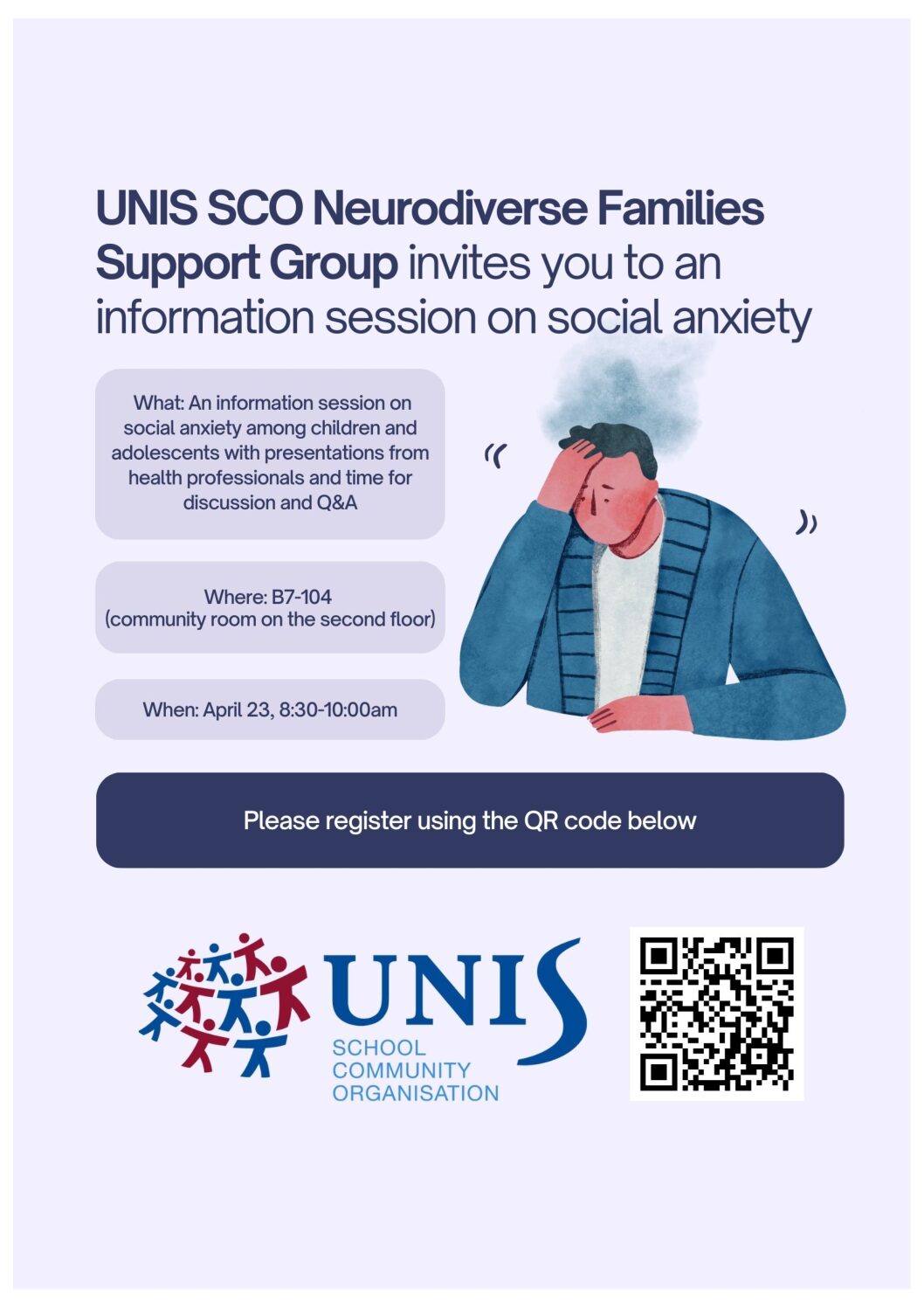私はニューロダイバージェントの親子を支援する立場に置かせてもらっていますが、私自身もニューロダイバースな子どもの成長や環境の変化とともに常に新しい挑戦と向き合っている保護者の一人です。
常に学び続けていても、解決策が見つからないことがあったり、自身の子どもの心配ごとは耐えることがありません。教師として教科担任をしていたときは自分が持っている知識や理解に頼っていられましたが、ニューロダイバースな子どもの発達支援は学校の授業とは違い、チームで他の専門知識を持っている人とお互いに頼り合いながら支援する大切さを実感しています。
私が前に進み続けるための原動力の一つに、他の保護者(特に私の前を歩いている保護者)との交流の時間があります。いままで様々な考え方や気付きをもらいました。時には疲れているときに寄り添ってもらったり、前に進む勇気をもらって帰ってくることもありました。
よくインターナショナルスクールでは、ラーニングサポートの先生から診断がついたら、学校でどのように支援を入れたらよいかわかるように心理教育的検査(Psycho-Educational testing)を受けてくださいと言われます。私もアセスメントの重要性は理解しているのですが、飛行機代や一週間のホテル滞在費に検査費用、それも全額手出しで受けるとなると実際悩みました。
しかし、今日はその迷いを取り除いてくれる考え方を持つ保護者からの学びがありました。それは、診断がついたらEd-Psych Assessment(Psycho-Educational Testingの他の呼ばれ方です)で自分の得意や不得意を把握することで本人が最善な人生ロードマップに乗りやすくなること・選択しやすくなること、また自分の得意を活かしたレールに乗りやすくなることでうつや燃え尽き症候群を減らすことができるということです。学校が終わってからの人生のほうが長いので、できれば早いうちから自分の得意・不得意を理解しておくと、仕事の選択もより自分の得意に合わせた方向に目を向けることができるのではないでしょうか。
“ADHD isn’t something to be fixed – he needs to see this and know that he is perfect just as he is. But yes, a full evaluation will tell him things about his profile that will help him for the rest of his life. It’s the road map that will help him set up his life in the best possible way. If he doesn’t have a clear picture, my fear for him is that he will be a “fish trying to climb a tree” following the crowd, vs. following the path that fits his strengths, and that can lead to burn out and depression. – by a parent of ADHD college student”
子どもはいつかは自立して、私達の手元から巣立っていきます。その時までに、自己理解ができているように、不得意を補う知恵やスキルを教えてあげること、得意を活かせるように、支援を求めることは恥ではないことを理解してもらうように、親としてやれることがたくさんあると他の保護者から気付かされた一日でした。
4月のSENIA Monthly Lunchはタイホー地区のPizza Pomodoroであります。是非参加してみてください。