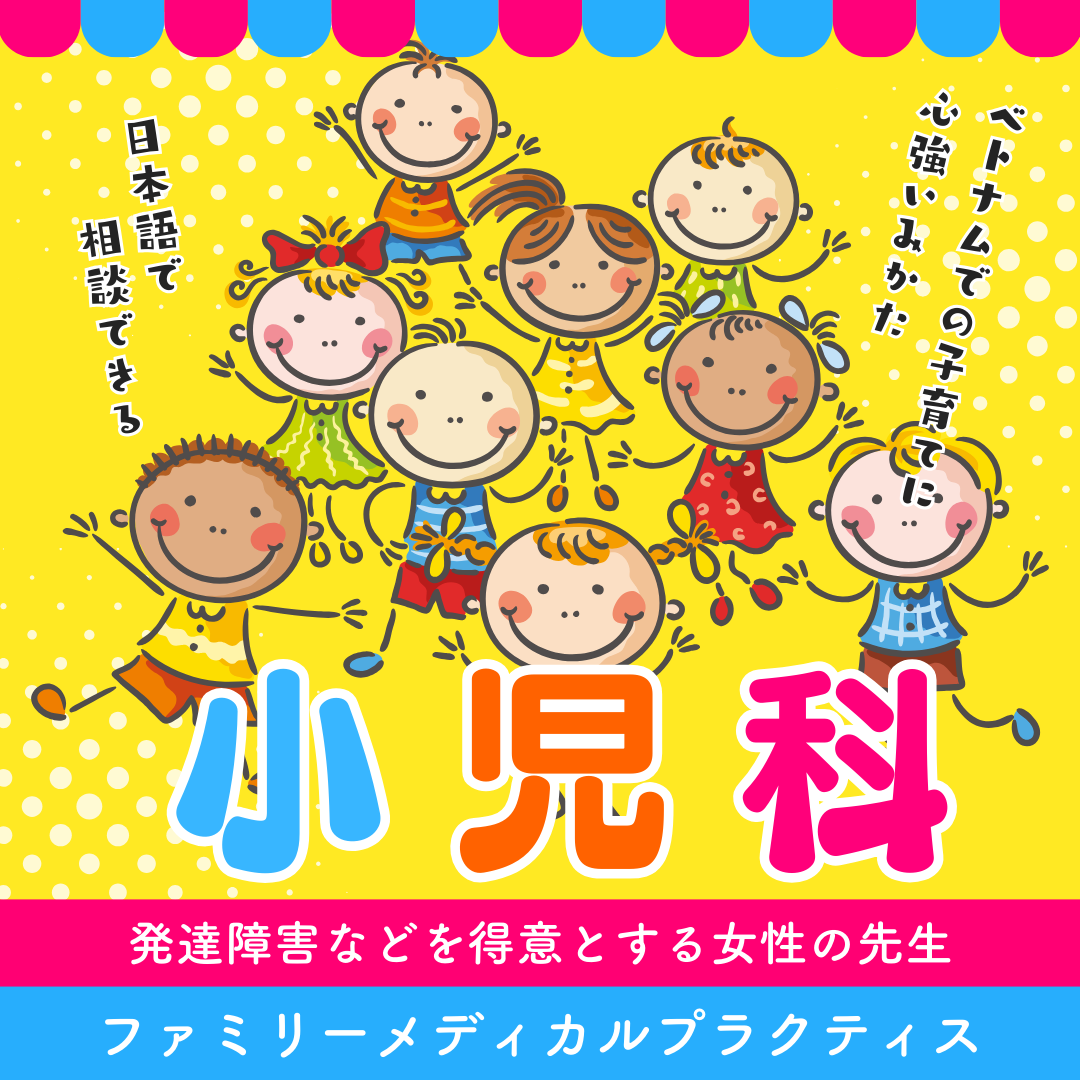実行機能のスキルについて先日書きましたが、今日は実行機能(Exsective Function:EF)について話されているTEDTalkをご紹介したいと思います。設定から日本語翻訳にしてご覧ください。
子どもが教室でそして生涯を通じて成功を収めるための鍵といわれているEFスキルは必ずしも学校のカリキュラムに含まれているわけではありません。息子の学校では、中学生になるとEFスキルの授業が週に一回行われています。学生時代にEFスキルの習得ができない場合は、生徒たちは社会に出てから自分でスキルを身につけるか、スキルを身につけずに苦労することになります。
このような事態を防ぐために、教室で使える魅力的なTedTalkをいくつか紹介します。
1. Feats of Memory Anyone Can Do
Executive Functioning Skills: working memory and sustained persistence(実行機能スキル:ワーキングメモリと持続的持続力)
2. Why Our Screens Make Us Less Happy
Executive Functioning Skills: emotional control and time management
(実行機能スキル:感情コントロールと時間管理)
3. How to Gain Control of Your Free Time
Executive Functioning Skill: time management, planning/prioritizing, and task initiation (実行機能スキル:時間管理、計画/優先順位付け、タスクの開始)
4. How to Get Better at the Things You Care About
Executive Functioning Skills: planning/prioritizing and sustained persistence (実行機能スキル:計画/優先順位付け、持続的な粘り強さ)