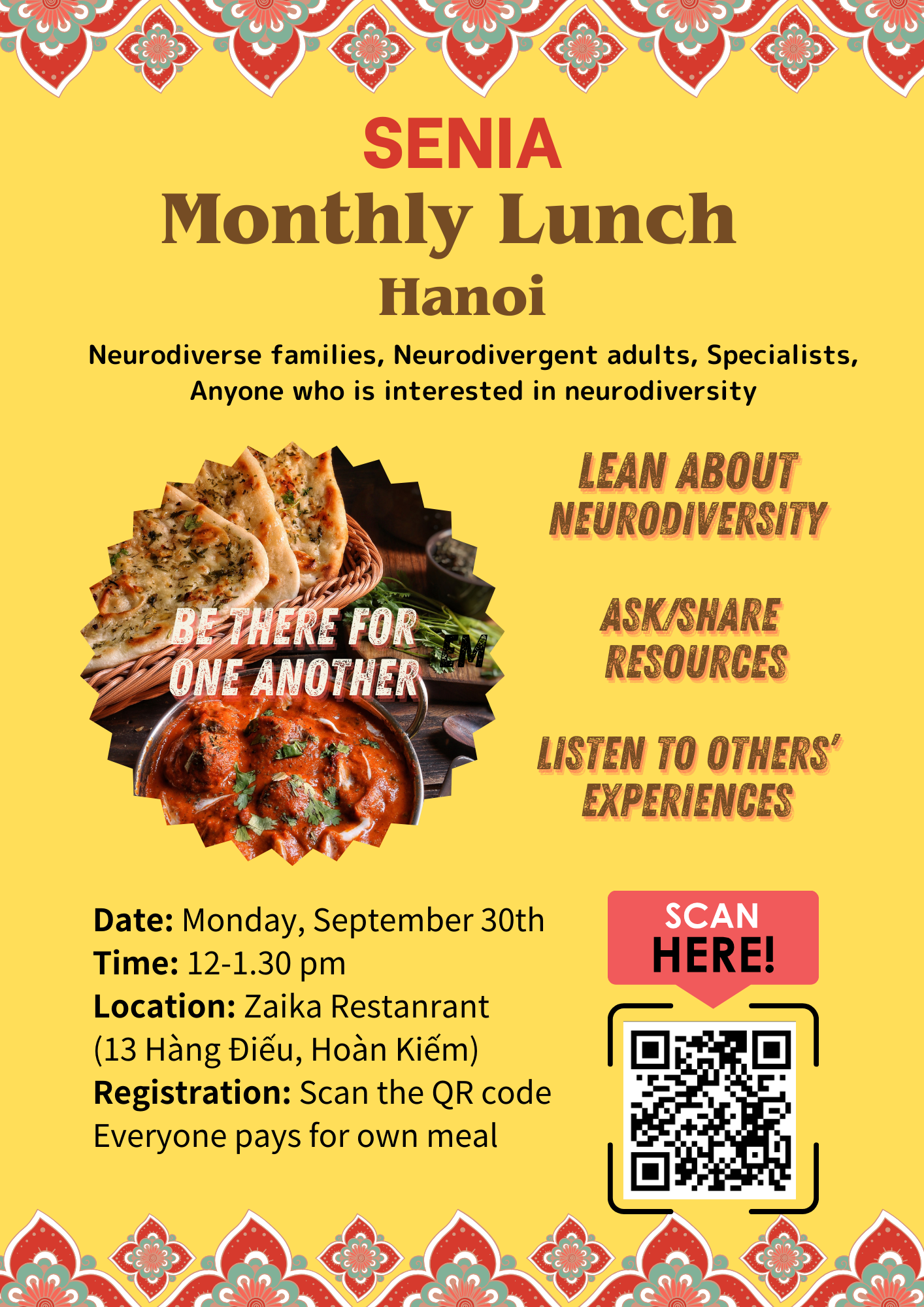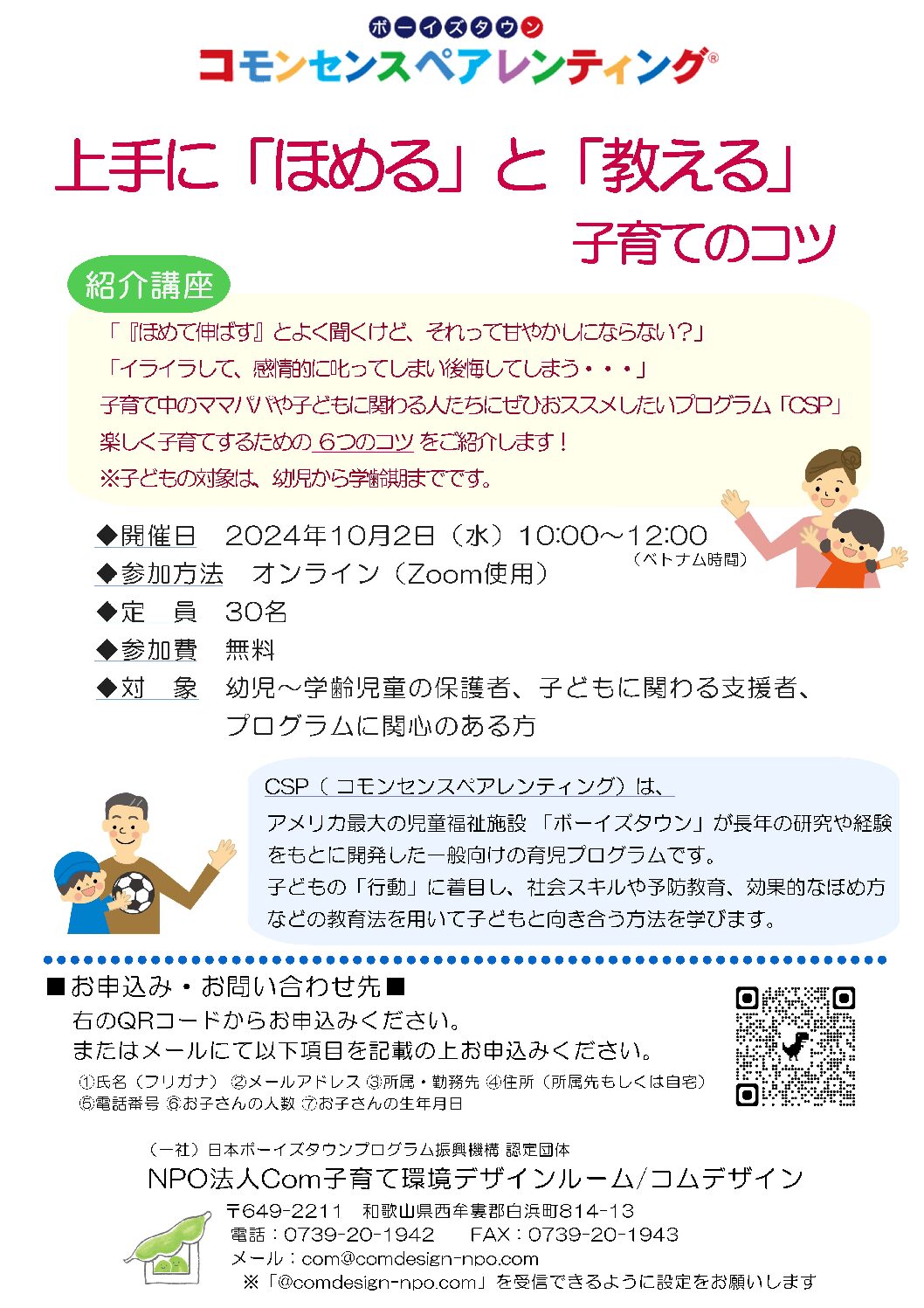2024−2025年度、SENIA Vietnam第一回のランチ会が9月30日(月)に行われます。
お互いの経験を分かち合ったり、
情報を共有したり、経験者に質問をしたり、
ニューロダイバーシティーについてもっと知りたいと思っている
保護者、ニューロダイバージェント本人(大人)、 専門家、 ニューロダイバーシティーに興味のある方
どなたでもご参加ください。
様々な国の方が参加されています。
日時: 9月30日(月)12-1.30 pm
場所: Zaika Restanrant (13 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm)
申し込み: ポスターQR codeより
参加費:自分のランチ代
共通語は英語になりますが、日本人窓口の千葉がおりますので、英語のサポートが必要な方は当日お知らせください。