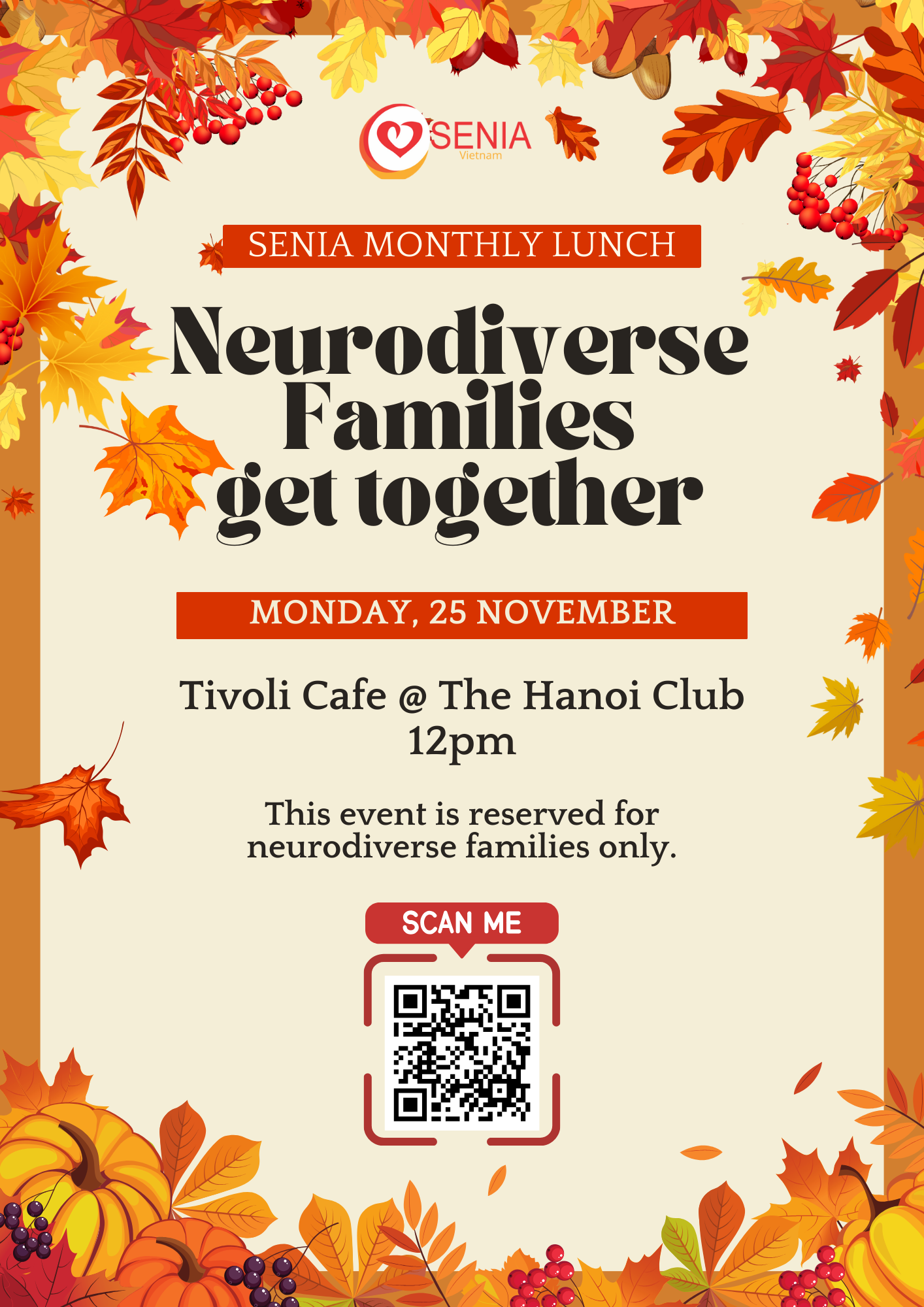皆さんのお子さんはハイハイをきちんとしましたか?
またうつ伏せ遊び(親が見守る前でうつ伏せの状態にして、眼の前におもちゃや鏡などを置いて一定時間遊ばせる)をさせましたか?
ハイハイがなく歩き始めたというお子さんやうつ伏せやハイハイの期間が短かったお子さんはちょっと注意が必要です。
というのも、ハイハイやうつ伏せ遊びをすることによって統合される原始反射があったり、首を上下に動かしてものを見る力がつくからです。原始反射が統合されず残っていると後で困り事が出てきたり、首の力がついていないと黒板と机を目で行き来するときに疲れてしまったり、姿勢が保持できなくなってしまうからです。
乳児のお子さんを持つお母さんは、早く歩いたー!と喜ばず、しっかりハイハイやうつ伏せ遊びをする時間を取りましょう。