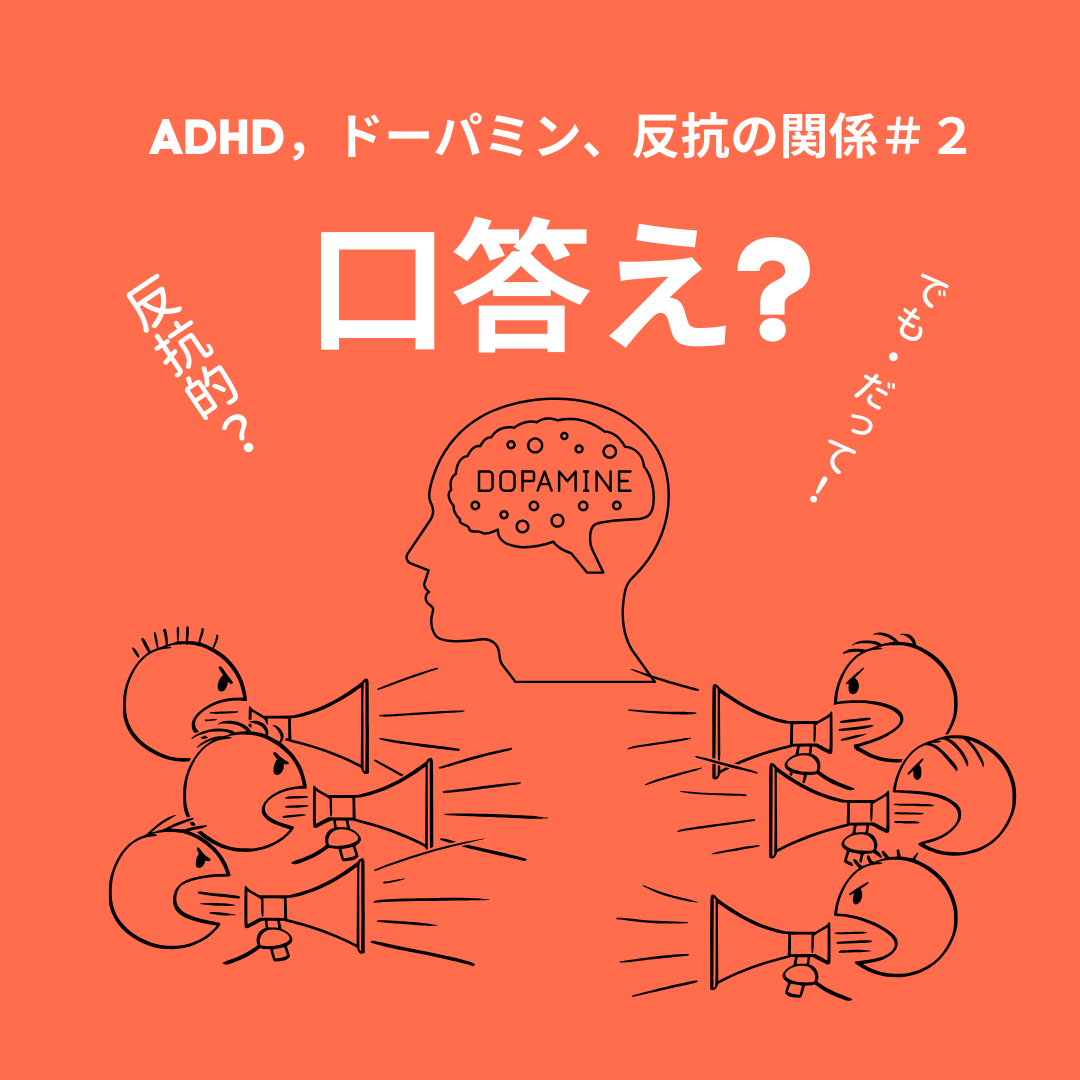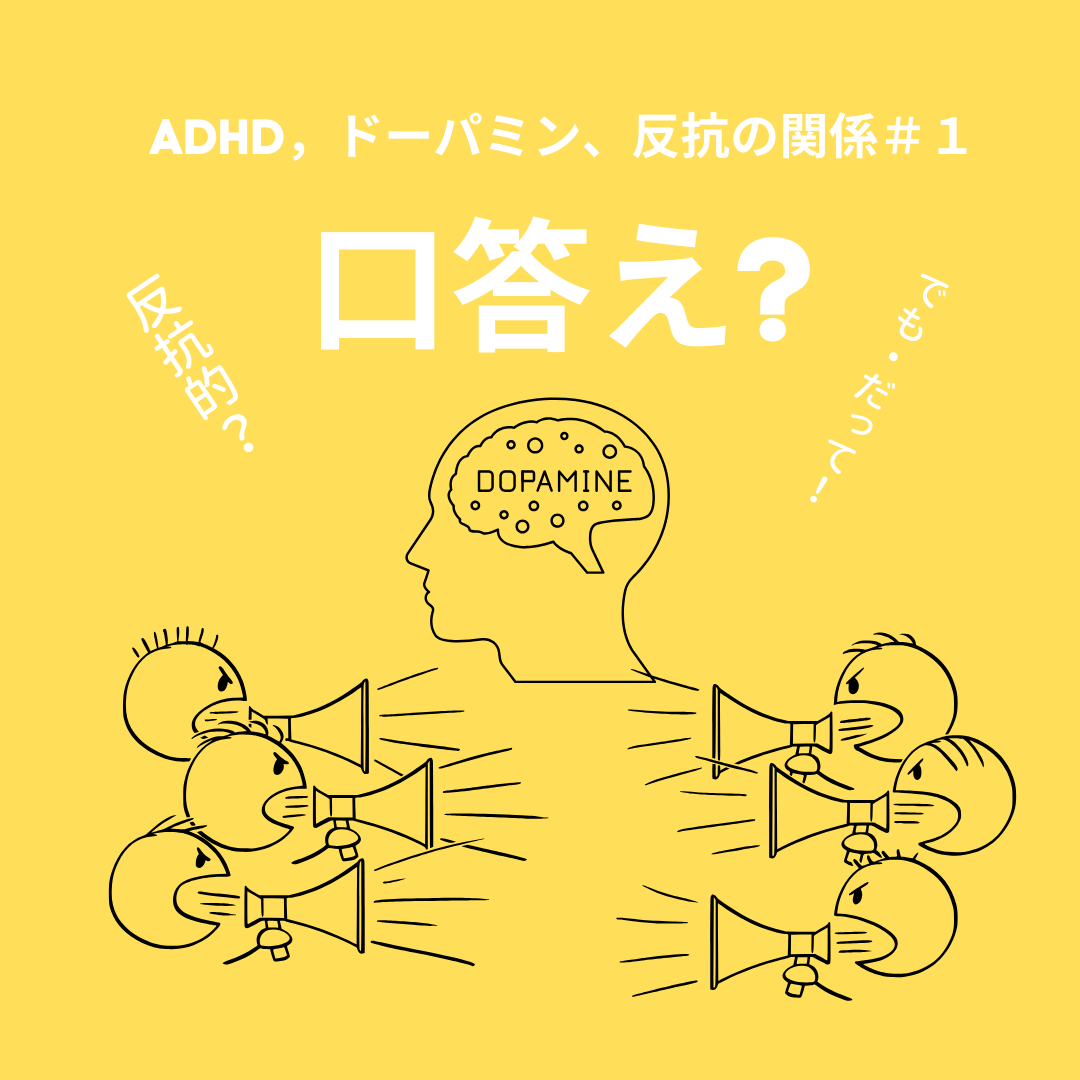前回の投稿の続きとして、今回は実際に子どもが口答えをしたときの返し方を簡単にステップでお伝えたいと思います。
みなさんも経験済みだと思いますが、ADHDの子どもが口答え・反抗的な態度をとったとき、自分(親)がどう返すかによってその後の流れが大きく変わってくると思います。大人が「対立する」「怒鳴り返す」と、ドーパミンを刺激してさらに口答えを強化してしまうこともあるので、落ち着いた対応はとても重要です。落ち着いて対応するには自分にも心の余裕があることが必要だと思っています。予定を詰めすぎない、自分のための時間を持つ、あなたは何ができるか考えてみてください。
それでは、 ADHDの子どもが口答えしたときの返し方を簡単に説明したいと思います。
ステップ1:感情を受け止める(共感←我が家はこれがないとうまくいきません)
子:「うるさいな!今やろうと思ってたのに!!」
親:「そっか〜、今やろうとしてたんだね。ごめん。言い方がきついとびっくりしちゃうよ。」
ポイント:まず「気持ち」は否定しない(反発されにくくなる)、ただし「言い方」は落ち着いて指摘する。
ステップ2:「選択肢」を与える(対立を避ける)
親:「今すぐやる?それともタイムタイマー5分かける?」
親:「やらないなら、次にやりたいこと(ゲームなど)も遅れちゃうけど、どうする?」
ポイント:命令(〜しなさい)よりも選択肢を出すことで、反抗する理由を減らします。自分で決めさせることで、自主性と落ち着きが生まれやくなります。
ステップ3:行動より先に落ち着くサポートをする
子:「うるさいって言ってんだろ!!」
親:「今イライラMAXだね。落ち着けるように深呼吸するから一緒にどう?それともちょっと落ち着けるまで部屋にいる?」
ポイント:反抗の裏には「イライラ・不安・疲れ」などの感情があるので、学校から帰ってきたらすぐ習い事にと急かしたり、今すぐ宿題をやりなさいと迫らない。お菓子、飲み物、休憩、などの時間を確保する。まず心を落ち着かせることが優先です。
コツとしては、“火”に“火”を足さない
NGな返し→火を強くする、 OKな返し→火を鎮める
「なんでそんな言い方なの!?」 ⇔「言い方が強かったね、何が嫌だったの?」
「言い返すんじゃない!」⇔ 「そっか〜。じゃあどうしたい?」
「怒るならもう何も言わない!」 ⇔「イライラしてるのはわかった。ちょっと休んで」
言い方の違い、わかりますか?
反抗は、コントロールできない感情や欲求があふれた結果であるとも言われています。思春期などの反抗期もありますが、大人が落ち着いて接することで、安全で安心な環境が生まれ、少しずつ反応も落ち着いていきます。我が家には反抗期真っ最中の子どもがいます。私も落ち着いて接することができるよう、日々の生活の見直しをして、自分に余裕があるよう努力しています。