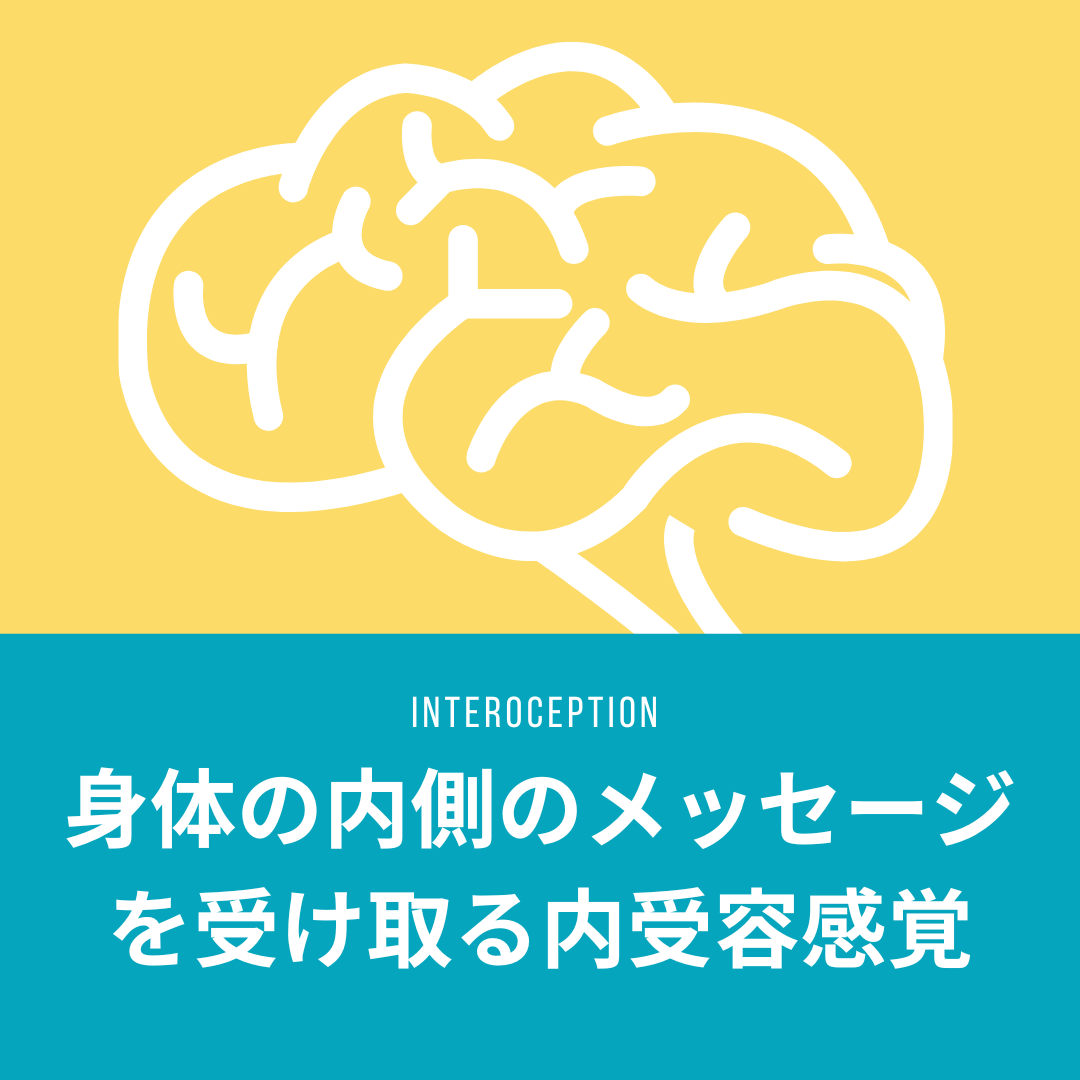来月3月17日から21日はニューロダイバーシティーウィークです。
ニューロダイバーシティーって聞いたことがあるけれど、何だろう?って思ったことありませんか。海外ではよく発達障がいなどを持つ人達のことをいいますが、日本のニューロダイバーシティーサロンや子ども・青少年育成支援協会の定義には、ニューロダイバーシティ(neuro-diversity)とは、「脳多様性」や「神経多様性」などと訳される言葉で、具体的には「脳や神経の在り方には、人それぞれに違いがあり、それらは人間の多様性の一つとして尊重されるべきである」とする考え方を指します。つまりこの考え方は、発達障がいのある人のみならず、すべての人を対象とすることを前提としています。
周りに、または家族にニューロダイバーシティーが存在しているかも知れません。是非ニューロダイバーシティーウィーク中に、子どもと話し合ってみたり、発達障がいのお子さんをお持ちの保護者は下のポスターを使って、家族の中でそれぞれ自分がどこの段階にいるのかを話し合ってみてください。