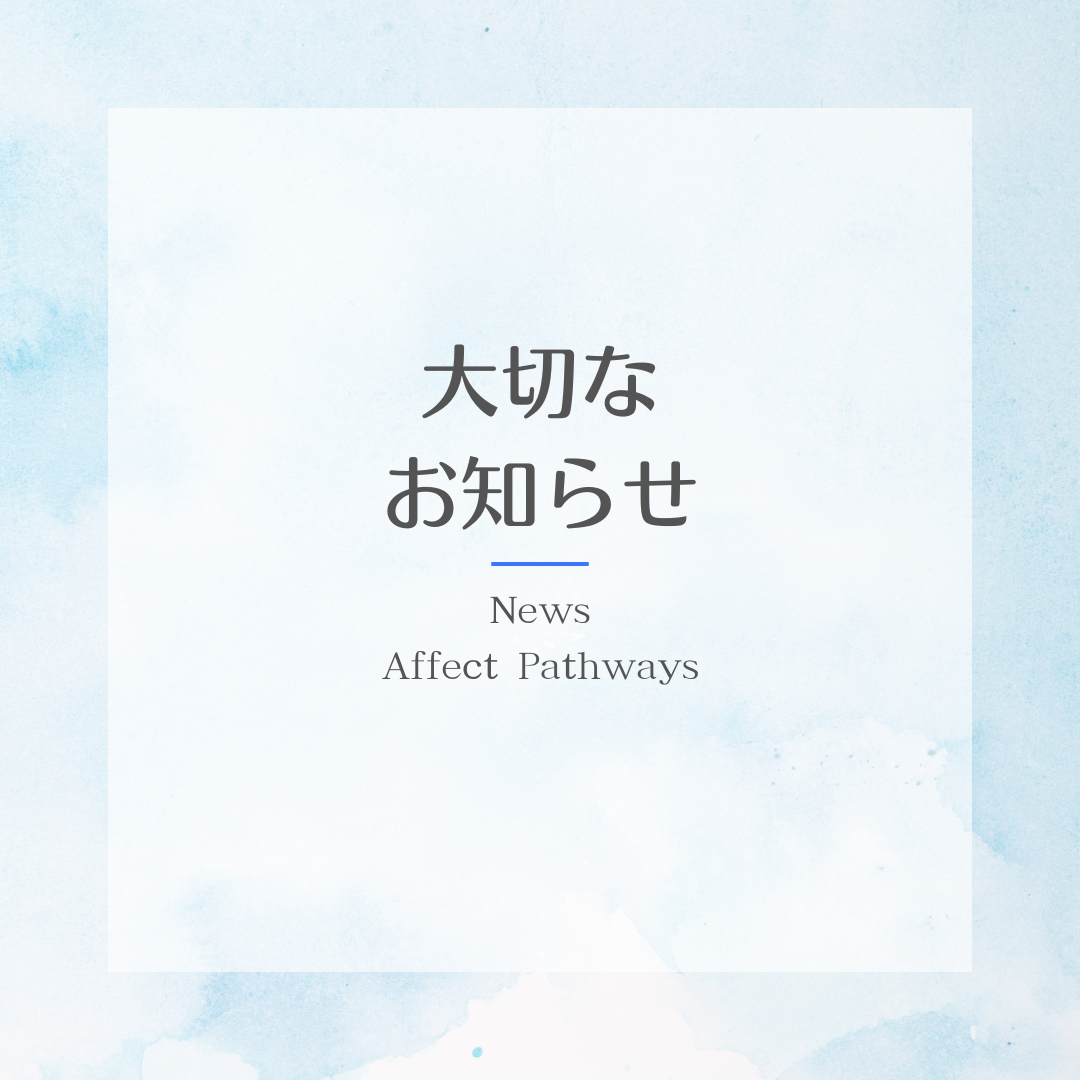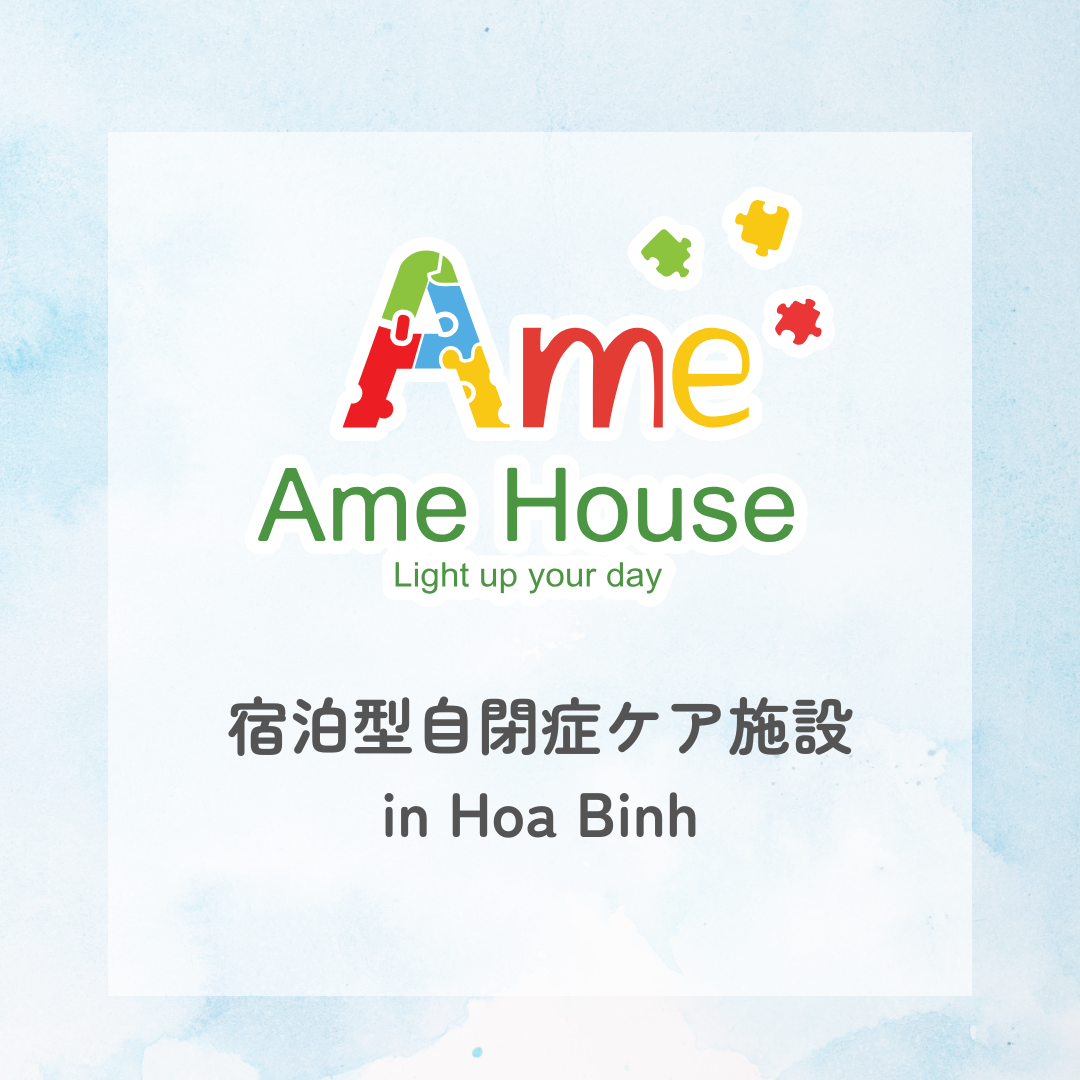ここ数年、ハノイでは徐々に認可を受けた療育施設の運営が開始され、市内では日本人の作業療法士(OT)による支援も提供されるようになりました。嬉しい限りです。これに伴い、Affect Pathwaysの活動を休止し、日本へ長期一時帰国することとなりました。活動の再開の是非につきましては、今後ハノイでの需要があるかどうかを見て決める予定です。
発達障害者の受け入れ、理解、また学校でのフルインクルージョンへの道のりはまだまだですが、ハノイ市内で支援の輪が少しずつ広がっていることをとても嬉しく思います。この3年間、様々な専門家と一緒に活動をしたり、他の保護者との出会いがあり、支援提供者、また発達障害の子どもを持つ親として成長させられたことに感謝したいと思います。ご支援、ご協力くださった皆さま、ありがとうございました
hẹn gặp lại
敬具
Affect Pathways Family Support Services
千葉敦子